こんにちは!
谺(こだま)こと、児玉朋己です。
今回は、
「シン・病者の教養とは?その3」
をお届けします。
実は、
昨年11月の始めに、
旧い友人から以前の記事、
「シン・病者の教養とは?」
に対する、
たいへん丁寧な感想をいただきました。
今回はその感想への応答です。
その友人は、
「シン・病者の教養とは?」で参照している本における教養の考え方には大きな問題があるのではないか?
と問いかけてくれました。
そして、
本来の教養にふさわしくもっと深く考えてほしいと、
参照するための材料も紹介してくれました。
今回は、
それをふまえて教養について考え直したというわけです。
その結果私が得られた核心は、
「シン・病者の教養とは?」
「シン・病者の教養とは?その2」
で取り上げた、
「教養には目的がない」
という定義が間違っているという見識です。
またそれに加え、
これまでの記事で参照してきた本で述べられ、
一般的にも考えられている、
「個人が、興味の赴くまま無目的に楽しんで書物を読み、結果的に身につけた知識の集まり」
という教養の定義・イメージは、
きわめて限定的な狭い概念だったという認識も得られました。
では他にどんな教養があるのでしょう?
今回はそれについて見ていきます。
※本ページではアフィリエイト広告を利用しています。
『「教養」とは何か』
今回取り上げるのは、
『「教養」とは何か』(阿部謹也著)
です。
くだんの友人は、
というPDFファイルを紹介してくださいました。
コンパクトなのにたいへん含蓄に富んだ内容でしたので、
本になっている『「教養」とは何か』も読んでみました。
すると、
こちらはやはり著者が自分の考えを十分に展開している感じがありました。
そこで、
今回は書籍のほうを取り上げることにしました。
内容は、
教養を、
「世間の中でいかに生きるか」
という問題意識から見つめたものになっています。
西欧中世の話が多いですが、
あくまで日本の「世間」を問題にしています。
以下、
各章を要約したり引用したりしていく形で本全体を紹介していきます。
引用部分ははっきり示します。
それ以外の部分には、
本の内容を私が要約・説明した文章と、
私自身の感想とがあります。
私の感想は太字にしました。
友人の心遣いと著者の思いに十全に応えたく、
かなり長くなってしまいました。
お付き合いくださると嬉しいです。
長いので今回は動画はお休みです。
序章 建前と本音
著者はまず、
私たちは建前と本音の使い分けが必要な「世間」の中で生きている、
といいます。
そして、
我が国には二種類の人間がいて、
建前としての正義や公正の原理を主張する人と、
そのような主張をする前に正義や公正がどのような条件の下で実現できるかを考えた上でなければ発言しない人がいる、
といいます。
「世間」と建前と本音
著者は以下のことを確認していきます。
- 我が国においては個人は長い間西欧的な個人である前に自分が属する人間関係である「世間」の一員であったこと。
- 何かの会合で発言する際には個人としての自分の意見を述べる前にまず自分が属する「世間」の利害に反しないことを確認しなければならないこと。
- 自分自身の意見は本音として「世間」の蔭に隠していること。
こうして「世間」を代弁する発言は建前となり、
建前と本音の区別が生まれたのだというのです。
これらをふまえて、
私たちが考えなくてはならないのが、
こうした「世間」の中での個人の位置である、
といいます。
これが著者の問題意識です。
「世間」は生き残り隠されている
著者は、
日本の近代化について振り返ります。
明治時代に我が国は欧米の諸制度を取り入れ近代化を図りました。
しかし欧化といってもそれは法制や行政構造・産業・教育制度などに限定されたといいます。
近代化は人と人の関係のあり方にまでは及ばなかったのです。
いわゆる和魂洋才です。
人間関係については従来の形=「世間」は生き残ったのです。
これは、
私たち自身の実感としてその通りだと思えますね。
著者はこのように、
近代化の流れの中でも「世間」はなくならなかったことを確認し、
次のように続けます。
大切なことは、
当時も今も「世間」は隠されていて、
私たちは自分が私的生活の足場である「世間」を持っていることを隠し、
あたかも建前の世界だけで生きているかのように振る舞っているということです。
私たちは二重生活を強いられているのです。
言葉は言葉それ自体として受け止められず、
その背後にある真の意図が常に探し求められるようになりました。
発言の真意とか趣旨といわれるものです。
我が国の文化が抱えている問題の根元に、
この「世間」の問題があるのです。
教養と「世間」
著者は、
教養と「世間」の問題がつながっていることを、
あらためて次のように確認して序章を結びます。
我が国の社会を捉える方法について考える際に、
教養の問題を通して「世間」の問題に接近する方法を探ることにしたい。
教養の問題と「世間」の問題とは不可分だから。
第一章:公共性としての「世間」
第一章では、
ハーバーマスの公共性の考え方を取り上げながら、
日本の歴史の中で「世間」がどう捉えられてきたか検討していますが、
略します。
第二章 「世間」の中でいかに生きるか
1 個人の教養と集団の教養
著者の問題意識は「世間」の中での教養です。
そのため、
次のように問いを立てます。
「世間」の中でいかに生きるかという問いを立てた場合、
私たちにできることはなんだろう?
「世間」について考えようとすると途方に暮れてしまう。
そこで、
そもそも「いかに生きるか」という問いはどのように形を持ちえたのかを考えたい。
教養の始まり=「いかに生きるか」という問い
ここから、
西欧中世についての考察が展開していきます。
それは、
西欧社会が日本に大きな影響を与えたからです。
著者によると、
人類の歴史の中で「いかに生きるか」という問いが実質的な意味を持つことになったのは十二世紀頃が始めだったといいます。
西欧中世においてすら中頃までは、
父親の職業を継ぐのが普通だったそうです。
この十二世紀頃に西欧に都市が成立し、
そこで新たな職業選択の可能性が開かれたのです。
著者はいいます。
いまや何を職業とすべきかを考える中で「いかに生きるか」という問いが重要な意味を持つようになったと。
これは西欧においては極めて重要な画期だったといいます。
西欧社会において初めて個人が誕生し、
男女の恋愛も新しい局面に入っていたのです。
西欧社会はこの頃から個人と社会の関係に意を用いなければならなくなりました。
そこで「いかに生きるか」という問いが立てられたのです。
これが「教養」の始まりでした。
二種類の人々
ここから著者のユニークな問題意識の表明が始まります。
当時の西欧には二種類の人々がいたというのです。
著者によると、
人々にはこの「いかに生きるか」という問いを立てる必要のあった人とその必要のない人がありました。
問いが必要となったのは新たに生まれた都市の数少ない人々でした。
そして、
人口の大半である農業に従事していた人々には問いを立てる必要がありませんでした。
教養が「いかに生きるか」という問いに始まるとすると、
農業などの伝統的職業に従事していた人々に教養は無縁なものだったのでしょうか?
この問いを自ら立てる必要がなく人生を大過なく渡っていた人々のことを考慮に入れて教養を定義したい、
と著者はいいます。
教養の定義と二種類の教養
上記をふまえた著者による教養の定義は次のようなものです。
「自分が社会の中でどのような位置にあり、社会のためになにができるかを知っている状態、あるいはそれを知ろうと努力している状況」を「教養」があるというのである。そうだとするとそのような態度は人類の成立以来の伝統的な生活態度であったことが解るだろう。
(p.56)
著者はこの定義に込めた思いを語ります。
集団の教養
たとえば農業に従事している人を考えると、
彼らは自分たちの仕事が人々の生活を支えていることを知っていでしょう。
自分たちの仕事が社会の中でどのような位置を占めているかについては自ら考えをめぐらすことはなくても、
知っていたでしょう。
彼らはこうしたことを身体で知っていたから、
「いかに生きるか」という問いを立てる必要もなかったのです。
こうした人々の人生に向かう姿勢をあえて教養というとすれば、
それは集団の教養というべきものでしょう。
個人の教養=これまでの教養概念
これまでの教養概念の中心には、
文字があり書物がおかれていたと著者はいいます。
「教養がある」人とは多くの書物を読み、
古今の文献に通じている人を指すことが多かったといいます。
読書の結果その人は世の中を良く知り、
さまざまな事柄について的確な判断ができるとされました。
ときには「教養がある」人とは人格者でもあるとされました。
しかし、
歴史的に遡ってみるとこれらは個人の生活態度を教養とするものであり、
西欧社会の特定の時代に成立したきわめて狭い概念だったと著者はいうのです。
これは都市に住み「いかに生きるか」と自らに問わざるを得なかった人々の教養であり、
個人の教養というべきものだと。
教養にはこのように個人の教養と集団の教養との二つの種類がある、
というのが著者の見識なのです。
サン=ヴィクトルのフーゴー
さて、
十二世紀に個人の教養が生まれたということは、
集団の教養にも大きな影響を与えずにはおかなかったと著者はいいます
個人の教養の成立の転機に立っていたのは、サン=ヴィクトルのフーゴーである。フーゴーは個人の教養の出発点に立っていたと同時に集団の教養にも目配りが利いた、この時代としてはまれな人物であった。
(p.57)
フーゴーの生年は不明ですが、
ドイツの東ザクセンに生まれ、
ハルバーシュタット司教区のハーメルスレーベン律院で教育を受け、
後にパリのサン=ヴィクトル律院に移ったといいます。
多くの書物を書いているそうです。
フーゴーの思想の核心に、
「全世界は哲学するものにとって流謫(るたく)の地である」
という考えがあるといいます。
「祖国が甘美であると思う人はいまだ繊弱な人にすぎない。けれども、すべての地が祖国であると思う人はすでに力強い人である。がしかし、全世界が流謫の地であると思う人は完全な人である」といっているのである。最初の人は世界に愛を固定しており、次の人は世界に愛を分散しており、最後の人は世界への愛を否定している。
(p.59)
ここにはフーゴーの思想が最も鋭く示されている。このような姿勢に立って初めて個人の教養は強力な発言権を持ち得たのである。これは「世間」の否定であり、根底においてはそもそも現世否定につながりかねない思想である。このように根底において現世否定の思想を孕んでいたからこそ西欧における個人の教養の思想は徹底することができたのである。
フーゴーのいう「個人の教養」のありかたは「世間」を否定するものでした。
私はこの部分を読んで、
いわゆる西欧的個人というものが、
このフーゴーの思想を核心として持っているのなら、
「世間」の中で「世間」を否定せず生きてきた私たち日本人が西欧的個人になれなかったのは当然だと思いました。
2 個人の教養の歴史的展開
さて、
ここからは個人の教養が生まれた後、
西欧社会の中でこれがどのように考え捉えられ、
扱われていったかが語られていきます。
教養概念の端緒
まず、
教養という言葉自体の成り立ちについて、
教養という言葉はドイツ観念論哲学の中で徐々に作られていったものらしい。
(p.62)
といいます。
そして、
「個人の教養」概念の端緒として、
ベルリン大学を創始したフンボルトの考えを示します。
ドイツ観念論哲学と新人文主義者たちの考えでは教養は孤独の中で身につけられるものであり、それは「ひとり人間の自発的活動によってのみ獲得され、人間の知的な自己教育という形の中でのみ獲得され、人間の知的な教育という形でのみ達成されるもの」(ヴィルへルム・フォン・フンボルト)とされている。
(p.62)
そして、
観念論哲学者たちは、
その世界認識としての哲学は大学で行われるべきものとしたといいます。
ここから大学の「孤独と自由」という議論が生ずるのであるが、そこにはもうひとつの重大な半面がある。それはこの「純粋な学問」という概念には、「実際の生活に直接関係をもち、実際の生活に応用され、そしてそれと共に特殊専門化された学問に対する拒否」(シェルスキー)が含まれているからである。「純粋な学問」は日常生活を遥かに超越しており、日常生活には直接影響を与えるものではないという考え方だったのである。
(p.63)
「純粋な学問」というイメージ。
私自身も若かりしいつか・どこかで学問についてこのようなイメージを与えられてた記憶がありますが、
このイメージにも生まれた瞬間があったんですね。
教養と大学
さて著者によると、
フンボルトの「学問による教養」という考え方が生まれる以前には、
ドイツでは啓蒙思想によって多くの大学が作られていたそうです。
また大学の外にも学問の場が求められ「王立アカデミー」などが生まれ、
そこからはベーコンやデカルト、スピノザ、ホッブズ、ライプニッツなどの学者が数多く生まれていたといいます。
そんな状況の中、
フンボルトによりベルリンに一般教育を目的とした新しい教育施設(ベルリン大学)が作られることになりました。
その際、
フンボルトにとっては、
学問研究は暇のある個人が孤独の中で営むものだったといいます。
「いかに生きるか」という問いから遊離した学問教養
著者は、
もともと「いかに生きるか」という問いから始まった教養が、
大学と結びついた結果、
その問いから遊離していったといいます。
引用を続けます。
フンボルトにおける教養理念は「人間を実利的で、職業や社会的な利益などへの配慮にしか目が向かない生活から切り離し、「純粋に」倫理や理念に基づく生活規範に服従させようとする」ものであった。そのためにこのような教育を受けたものには実際の社会のありのままの姿に疎いところがあった。この点についてはすでにフリードリヒ・テンブルクの指摘があるが、それはこの種の教育が孤独の中で遂行されるべきだと主張されてきたことと深い関係があった。そしてこうした教養理念の背景にキリスト教があったことは明らかである。
(p.69)
こうして十八世紀末から十九世紀にかけてドイツで特定の市民階層が生まれていった。
教養とは本来「いかに生きるべきか」という問いに対して個人が答えようとするところで始まったものであった。しかしこの段階においてはそれはゲーテやシラー、レッシングその他の学者の作品の講読に固定化され、それらを読む読み方も定められ、学位という形で教養も個人の生き方とは関係なしに外から判定されるようになった。特に文学にまで学位が定められたことは決定的な意味をもった。文学博士という名称で教養のあり方が個人以外の大学という組織によって判定されることになったからである。教養はいわば国家によってからめとられてしまったのである。
(p.71)
またそれは、
当時の西欧社会によって歓迎されたことでもあったといいます。
それぞれの学問分野が当初の「いかに生きるべきか」という問いから遊離したことは国家や成立しつつあった社会にとっては歓迎すべきことであった。倫理的要素を排除したところで営まれる学問は単なる知識の集成として国家や社会にとって望ましいことだったからである。教養も同じ経過を辿った。倫理的要素を排除したところで営まれる教養こそ国家や社会にとって役にたつ人材を育てる手段となったからである。こうして教養もきわめて曖昧な形で人々が身につけるべきものとして位置づけられていった。しかし誰もが決して完全な教養人たることはできないような構造になっていたのである。
(p.73-74)
最後の一文が痛烈ですね。
問いから切り離された知識をいくら集めても、
「いかに生きるか」への回答は得られず、
本来の意味での教養ある人にはなれないということだと思いました。
日本の状況
さて、
著者は日本の戦前の教養理念のあり方についても語っています。
キリスト教の背景がない日本では、
『愛と認識との出発』(倉田百三)や『三太郎の日記』(阿部次郎)などの小説によって教養思想への動機付けがなされたといいます。
また、
福沢諭吉の啓蒙思想への反動によっても教養思想へのドライブがかかったそうです。
この点ではドイツと状況が似ていたといいます。
また、
明治・大正期の文部省と一部を除いた知識人たちは、
実用教育や産業の育成を第一義とは考えていませんでした。
この点でもドイツと同じ状況だったそうです。
夏目漱石や二葉亭四迷に代表されるこの頃の知識人たちは、
実業界を馬鹿にしていたのです。
3 文字によらない教養―身ぶりの世界
さて、
ここまできて著者は話をフーゴーに戻します。
それは、
集団の教養について語るためです。
先にフーゴーは集団の教養にも目配りが利いたといいました。
これを言い換えると、
フーゴーは「文字を必要としない分野」も哲学に入れていた、
ということです。
『ディダスカリコン』の中でフーゴーは哲学のすべての分野を修めた後陶工の道に進み、そこで修業する必要を説いている。あるいは哲学のすべての分野を修めた後靴直しの仕事に就く必要を述べている。
(p.78)
フーゴーによる哲学の区分の中には、音楽の実戦や狩猟、手工業、個人の実などが含まれている。これらは必ずしも言葉や文字を必要としない分野である。フーゴーがこれらの分野を哲学の中に入れていることはきわめて重要なことである。なぜなら、近代になって学問はほとんどすべて言葉や文字、記号などによって営まれるものとされているからである。
ここで特筆すべきことが語られています。
フーゴーは、
哲学のすべての分野を修めた後で陶工の道に進みそこで修業しなさい、
あるいは哲学のすべての分野を修めた後で靴直しの仕事に就きなさい、
と述べているのです。
それでなければ教養は完成しないと。
これは、
現代に生きている私たちにとってはちょっと面喰うことではないでしょうか?
フーゴーのいう哲学のすべての分野には、
文字で学ぶ教養もあれば、
さまざまな実践により身につける技術なども含まれていました。
それらを修めた後、
さらに修行せよ・実際に働けといっているのです。
私たちは座学として知識を学ぶことを教養の中心だと捉えています。
それとはまったく違う、
斜め上のしかもとても高いところから、
フーゴーは教養を捉えているのです。
さて、
文字によらないのが集団の教養です。
教養・知識なのに文字によらないのなら、
いったいどうやって学び伝えるのでしょうか?
中世は身ぶりの文明だった
それが動作や身ぶりでした。
中世は身ぶり文明だったと著者はいいます。
その実例として石工について取り上げています。
中世の末から近世にかけても石工のコミュニケーションには、動作、特に舞踏が大きな位置を占めていた。そのことはすでに別の書物で明らかにしておいたが(「中世を旅する人びと」平凡社)、遍歴してきた石工職人は文字が読めなかったから、自分の身分を証明するために仲間の職人たちとともに踊ったのである。皆でともに踊り、新入りの職人がステップを間違えなければ正当な職人として認められたのである。動作や振る舞いは手工業者だけでなく、王侯貴族の場合も重要な位置を占めていた。
(p.79)
また次のようにもいいます。
現代の世界と違って、文字以上に身ぶりが人と人の関係の全体を拘束していたのである。実際、文字は聖職者の占有物であり、一般の大衆にとっては全く無縁のものであった。一般大衆も含めて当時の人々は皆何らかの団体に属していたから、すでに述べた石工の組合のようにその団体の中ではすべての関係が儀式化されていた。その儀式は基本的に身ぶりであったから、身ぶりによって社会関係が保たれていたのである。
(p80-81)
さて、
著者は、
身ぶりは現在でも西欧で強い働きを持つけれども、
それは日本でも同じだといいます。
その例として、
- 世間
- 教養(茶道・能・その他の「道」)
を取り上げています。
また次のようにいって、
その実例として葬式と婚礼を上げます。
そして次のようにいうのです。
明らかなことは「世間」の中で生きるためには必ずしも西欧的教養は必要がないということである。では、「世間」の中で生きるために必要なものは何かといえば、いうまでもなく、文字や言葉を介さない教養である。つまり我が国においても「世間」の中で生きるためには文字や言葉よりは動作や振る舞いのほうが遥かに重要なのである。
(p.94)
学校教育と「世間」
さて、
上記引用を敷衍すると、
文字により表現された西欧的教養では「世間」を扱えないことになります。
実際その通りで、
著者はそれを教育と関連させて語ります。
家庭教育での例も上げていますが、
ここでは学校教育の現場での例について紹介します。
明治以来の学校教育では、
「世間」の問題はあたかも存在しないかのように扱われてきたと著者はいいます。
建前としての西欧風教育がなされ、
存在していない西欧風個人があたかも実在しているかのように教育がなされてきたのです。
小学校から中学高校の教科書もすべて西欧風個人を前提として書かれ、
実生活においてはほとんど役に立たないものだったといいます。
たとえばゴミ処理の問題が地理の教科書などで扱われたとする。一つの地域としてゴミ処理場が必要であることは述べられても、それに反対する地域の人々をどのように説得してゆくのかといった具体的問題はほとんど取り上げられないのである。取り上げられるとしてもそれは一般的、抽象的な立場からであり、ゴミ処理場がいかに必要かといった観点からであって、近隣にゴミ処理場ができた時の人々の反応についてはほとんど考察されていないのである。
(p.98-99)
私はここで目から鱗がボロボロと落ちました。
ゴミ処理場でも障害者施設でも、
反対していたのは「世間」だったのだと。
公共の施設として福祉のための施設として必要だと建前上は理解はしても、
本音としては自分の地域に建てられるのには反対する。
その反対している人は西欧風個人ではなく「世間」の人だから、
西欧的教養の言葉(公共性・基本的人権など)では説得できないのです。
また、
もとより学校教育で扱う西欧的教養では「世間」について語れないのだから、
解決法を教えることなどできないというわけです。
4 魏の君子の生き方
この項では、
前項で語られた西欧風教育の限界をふまえて、
それでは実際に「世間」の中で生きていくにはどうしたらよいのか?
という疑問に複数のヒントを示しています。
それは、
公私にわたる付き合いの中で、
おそらくは著者が恩師だと思っているだろう、
ある大学教授からの示唆に基づいた著者の思索です。
著者の恩師への深い思いがにじみ出ている部分なので、
要約が難しく、
ここでは割愛いたします。
興味のある方はぜひ本書を手に取ってください。
第三章 個人のいない社会
1 サガにみる個人と社会
第三章に入るにあたって、
著者はあらためて次のように問いを立てます。
我が国の「世間」は文字によって結ばれている人間関係の社会ではなく、文字以外の媒体によって結びあわされている社会である。そこには今でも西欧的な意味での個人は成立していない。そのような社会において人々はいかに生きるべきかという問いにどのようにして答えてきたのだろうか。
(p.120)
社会の中に西欧風個人が生まれる前にも社会はあったし人はいました。
その当時の人々はどのように生活していたのかという問いです。
この問いについて考える史料があると著者はいいます。
それがサガです。
サガとは、
エッダやスカルド詩などと並ぶ古ノルド後による散文詩だそうです。
サガは個人が未だ成立していない社会について後になってから文字による史料が残されている稀有の場合なのである。アイスランドサガとして知られる散文はアイスランド植民時代(八七〇-九三〇年頃)囲碁のアイスランドにおける出来事を十二~十三世紀になってから書き記したものである。
(p.121)
著者はこういってアイスランドサガを取り上げます。
サガは散文詩であり出来事を描写したものですが、
フィクションは意図的には入り込まないといいます。
サガにおけるフィクションは、
サガの創造者たちが真実の範囲内にとどまって許容できると見なしたフィクションです。
これを混合的真実といい、
アイスランドの人々はそれを言葉の本来の意味での真実と受け止めたのだといいます。
サガの特徴
この混合的真実のほかに、
サガには作者が氏名不詳であるという特徴があります。
これら以外に、
サガには次のような特徴があるといいます。
- 描写の中心は私闘。
- 個人は関係の中で描かれる。
- 個人の内的世界は語られない。独白はない。
- 個人は道義的な義務で動く。→現代の復讐とは違う義務。
- 名前は個性の一部。
- 自然の描写がない。
- 一定に均質的に流れる時間ではなく出来事と一体化し地層のように積み重なっていく時間。
2 サガの世界と日本の「世間」
著者は、
前項で述べた特徴について詳しく見るために、
「棒打たれのソルスタイン」
という物語をサガの実例として取り上げています。
長くなるので物語全体を引用できないのが残念です。
ストーリーは分かりやすく、
難解な言い回しもないのでスイスイ読めてしまいます。
そこで、
上記の特徴に留意して読み返してみると、
たしかに登場人物が現代の小説とは違うことに気づきます。
ストーリーは次のような感じです。
「棒打たれのソルスタイン」
主人公ソルステインが闘馬の最中に棒で打たれ、
「棒打たれ」という不名誉な渾名をつけられる。
しばらく我慢しているところに父親から復讐するようにそそのかされ、
相手のところまで出かけて殺す。
その相手のグループが復讐に来たがソルステインが返り討ちにして殺す。
相手のリーダーがその妻にそそのかされ再び復讐にやって来て決闘となるが、
決着がつかず和解する。
等々。
たとえば現代の小説なら、
闘馬に参加するならその時の理由とか心情とかが語られるでしょうし、
父親から復讐するように言われたらどうしようかと悩んだり葛藤したりといった様子が描写されるでしょう。
そういったことがなく、
相手とは闘馬をすることに決めたとしか描写されず、
闘馬の流れで相手に棒で打たれるといったことが出来事の羅列として語られるだけです。
復讐する動機も、
道義上義務としてそう動いているだけで、
内面の深い思いが独白されることはありません。
上記に示された特徴にも、
なるほど、
(西欧風)個人がいないとはこういうことなのか、
と理解することができます。
こうしてサガの実例を紹介した後、
著者はサガの特徴として次を付け加えます。
サガの特徴 その2
- 噂が重要。
- 国家のない世界での殺人=自力救済
噂が重要というのは、
上記物語の中で、
主人公の相手グループのリーダーが、
仲間内で「復讐しないなんて頼りにならない」という噂があるために復讐に動いた、
といったようなことです。
個人による殺人が自力救済だったという事情については次のように説明されています。
アイスランド社会における暴力にはきわめて強い特色があった。同時代の西欧各国と適ってアイスランドにおいては国境を拡張しようとしたり、国境を守るという発想がなかったのである。社会の内部も部族などに分断されてはいなかった。したがっていかなる形にせよ戦争と関わる暴力は存在していなかったのである。アイスランドに存在していたのは私的な関争であった。それは多くの場合殺人によって終わったが、それはバイヨックが述べているように「島国のタイプの私関の中で基力行為の大部分は社会を安定させてゆく結果を生んだ」のである。
(p.156-157)
アイスランド社会の特徴
さて、
アイスランド社会の特徴としては、
サガをはなれて他の資料を参照してみたときにも言えることがあります。
その特徴とは、
- 贈り物
- 宴席
です。
ここまでアイスランド社会の特徴を列挙してきました。
著者はここでアイスランドと日本との違いと共通性に話を進めていきます。
アイスランドと日本との違い
日本と違うアイスランドの特徴はこのようなものです。
- 外敵の侵入を恐れる必要がない。
- 人口が少なく国家がなかった。
- 部族もなかったから部族間の争いがなかった。
- 集団と自己とを一体のものとして感じていた
- 自然と一体な感じで暮らし、自然を対象として捉えていなかった。
アイスランドと日本の共通性
日本と共通性のあるアイスランドの特徴は次のようなものです。
- 人と人の間を結ぶ贈与・互酬の関係。
- 身分や名誉の意識
- 時間意識
参考になるサガの世界
著者はまとめに入っていきます。
サガの世界は近代的な個人が生まれていない社会として我が国の「世間」を歴史的に考察する上で参考になる社会である。そのような世界において個人と仲間集団の関係はどのように結ばれていたのか、また個人と仲間の名誉はどのように守られていたかという点に注目する必要がある。
(p.170)
サガの登場人物は自己を仲間集団と一体のものとして受け止めていた。したがって仲間集団が受けた屈辱は自分が受けた屈辱そのものであった。仲間集団の名誉のためには自分の生命を賭けることもいとわなかった。サガの世界では死後の生活も生前と同様に続くという信仰があったから、死は格別恐るべきものではなかったのである。人と人の関係が贈与で結ばれており、義が重んじられた世界であった。なによりも国家が生まれていなかったから、すべての事件は基本的に自力救済によって解決されていた。
直接には言っていませんが、
著者は、
「サガの世界は日本の「世間」とよく似ている」
と言いたいのではないかと私は感じます。
上で見たアイスランドと日本には違う点もありますが、
それ以上に人々は似た世界に住んでいるのではないでしょうか。
だからこそサガの世界は参考になるのです。
終章 「世間」と教養
ここは引用だけでまとめます。
「世間」は長い間現状を良しとしてきた。変革は望まれなかった。「世間」の現状がどのようなものであるかさえ問われなかった。それは人々の身体に付着していたからである。しかし「世間」が対象化され、客観的に分析しうるようになるとすれば、「世間」を変え、それを通して社会や制度を変えて行く道は開けてくるであろう。「世間」は柔らかな構造をもっているからである。そこでは「棒打たれのソルステイン」の話に見られるように何らかの制度ではなく、人間の質が最も重要な意味をもっているからである。
(p.179-180)
教養があるということは最終的にはこのような「世間」の中で「世間」を変えてゆく位置にたち、何らかの制度や権威によることなく、自らの生き方を通じて周囲の人に自然に働きかけてゆくことができる人のことをいう。これまでの教養は個人単位であり、個人が自己の完成を願うという形になっていた。しかし「世間」の中では個人一人の完成はあり得ないのである。個人は学を修め、社会の中での自己の位置を知り、その上で「世間」の中で自分の役割をもたなければならないのである。そのときはじめてフーゴーのいう靴直しや陶工として働くことができるのであろう。
病者の役に立つ教養も立派な教養(まとめ)
以下、
すべて私の言葉です。
この本で蒙を啓かれた見識がたくさんありました。
- 文字によらない知識も教養である。
- 文字による教養は特定の時代に限定された狭い概念だった。
- 文字によらない技術・スキル系も教養といえる。
- 実用と関係ない「純粋な学問」は特殊で一時的な教養理念だった。
- 個人が好奇心に導かれ学ぶという教養概念は偏狭だった。
- 世間の人との人間関係の中に言葉によらない教養がある。
- その人間関係の中で教養が完成する。
なんですね。
ということは、
このブログのテーマである、
病者の役に立つという目的に沿った「病者のための教養」も、
立派な教養だったということになりますね。
病者のための教養についての最初の記事、
「シン・病者の教養とは?」
では、
参照した本に書かれていた「教養には明確な目的がない」という定義に引っ張られていました。
そんなことを気にすることはなかったんですね。
堂々と、
「病者の役に立つ教養」を追求していけば良いのです。
良かった!
清々しました。
大きな問題について
最後に、
冒頭で言及した私の友人の問いかけ、
参照している本における教養の考え方には大きな問題があるのではないか?
が指していた大きな問題について説明します。
その本では
親方について学ぶしかなかった時代には親方以上、あるいはそ親方以外になることはできなかった、
本のおかげで学びが人間関係の縛りから解放された、
という意味のことが書かれていました。
また、
書物からの知識でなければ教養ではない、
という意味で語っている部分もありました。
友人はこの部分を指摘したのです。
こうした教養概念は、
きわめて一面的で狭く、
たしかに問題があったということが、
今回明らかになったと思います。
本を読んで学ぶこと以外にも、
いろんな体験・経験をして身体で学べば良いし、
必要に迫られて学ぶことに引け目を感じることはないのです。
指摘された問題は、
当該のブログ記事の内容自体に直接かかわるものではなかったので、
この最後でお伝えしました。
より深く学びたい人へ
友人が送ってくれた考える材料に動画リンクがありました。
今回のテーマについて語られたもので、
たいへん分かりやすかったです。
興味のある方はご覧ください。
長文になりました。
ここまでお付き合いくださりありがとうございました。
では、また!
生命って何だろう? 生きるって何だろう?
谺(こだま)
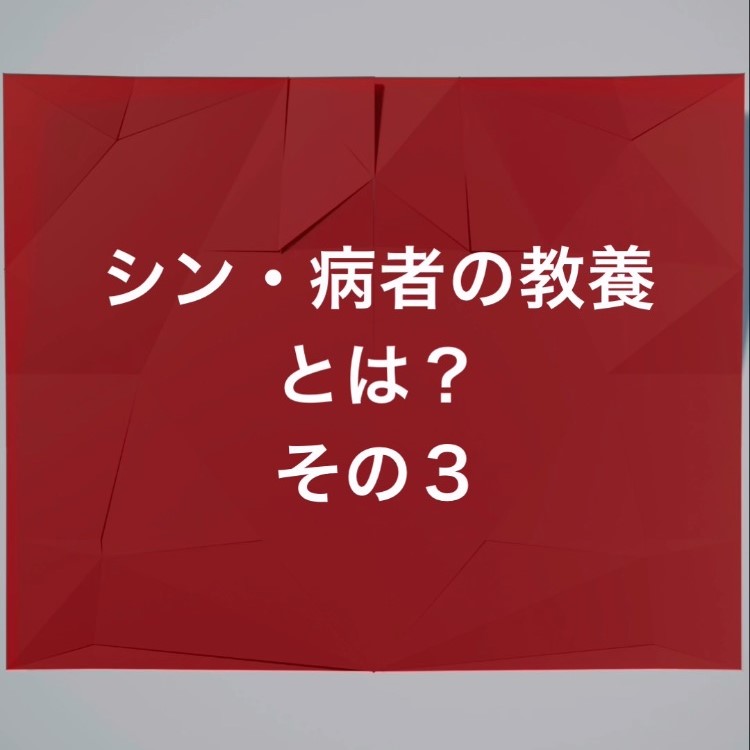
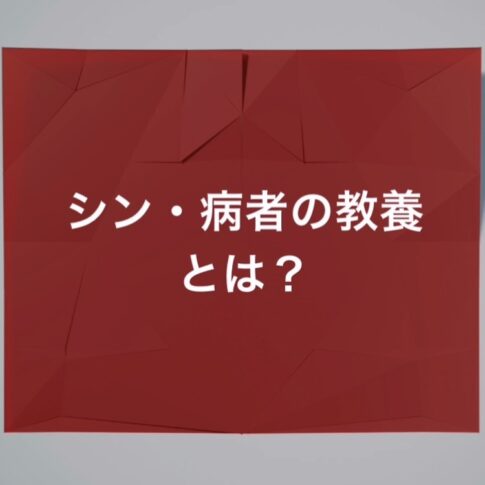
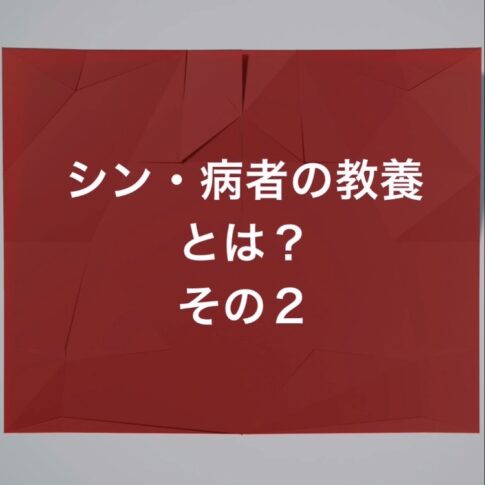


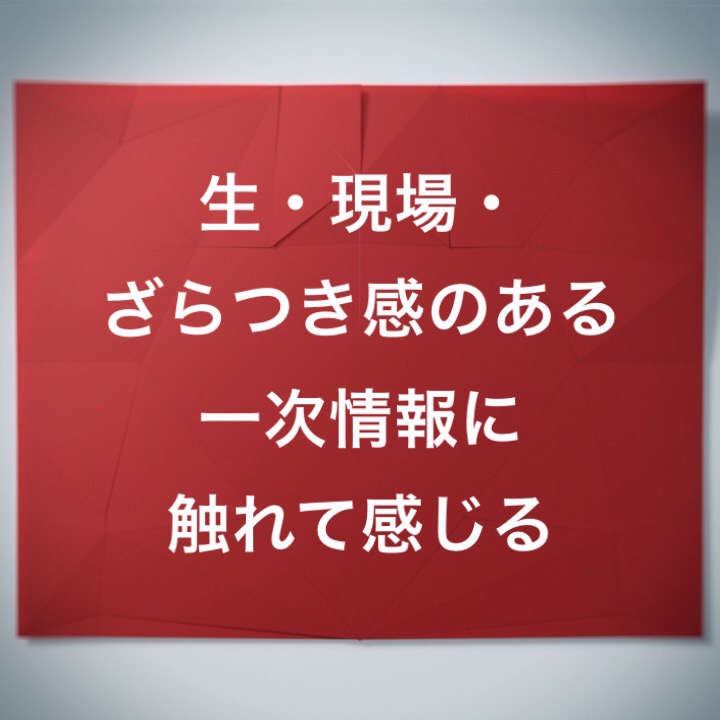
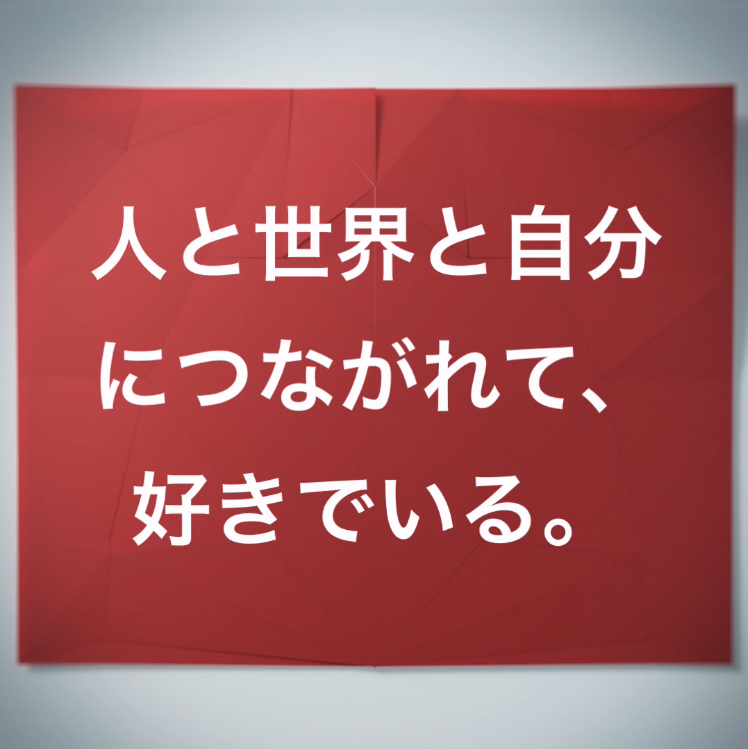
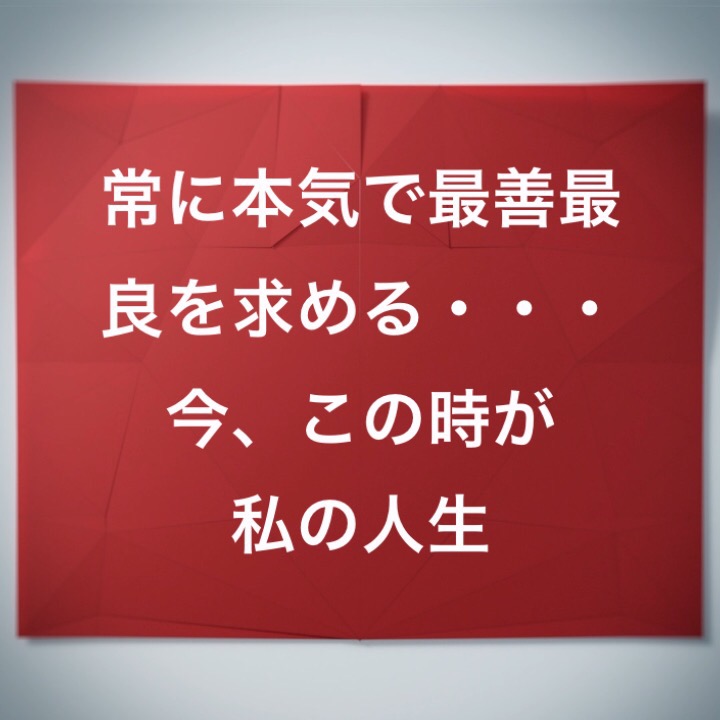
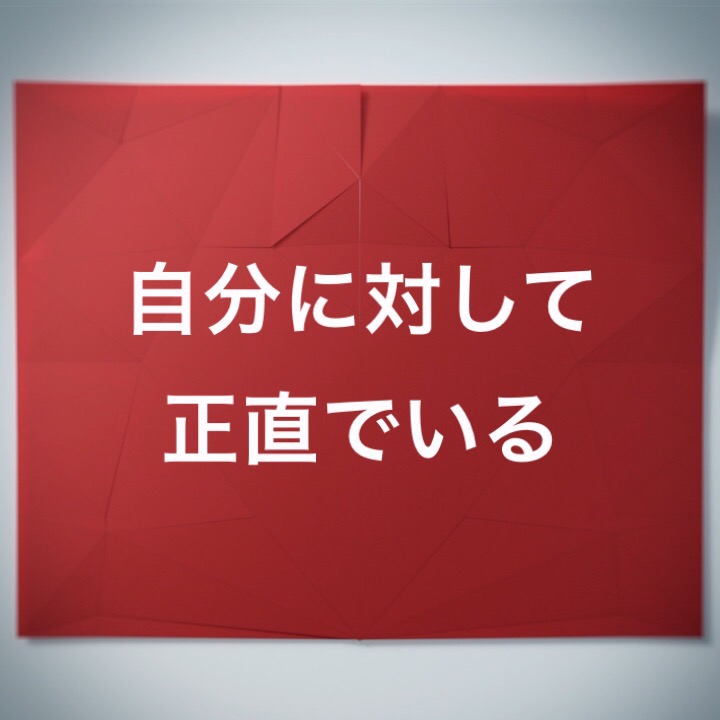
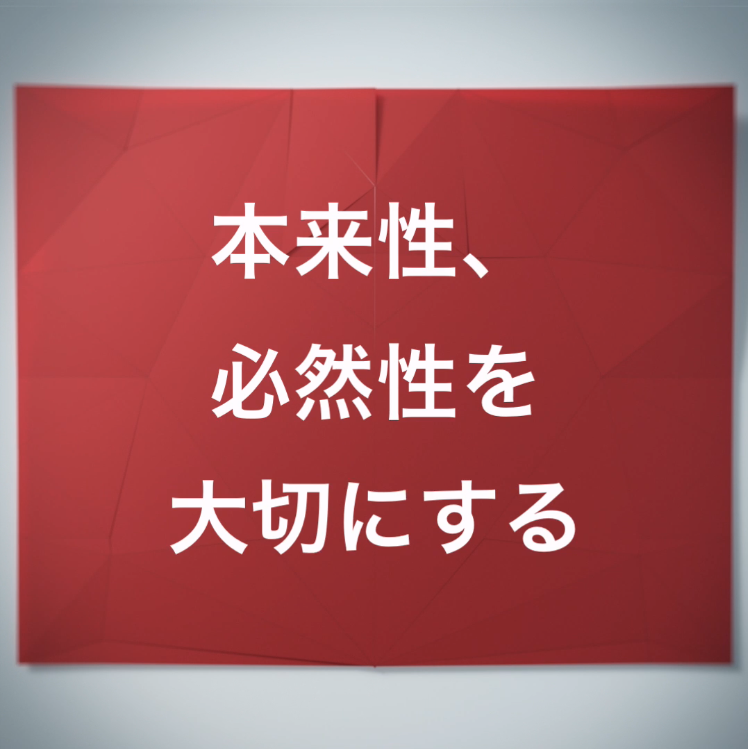


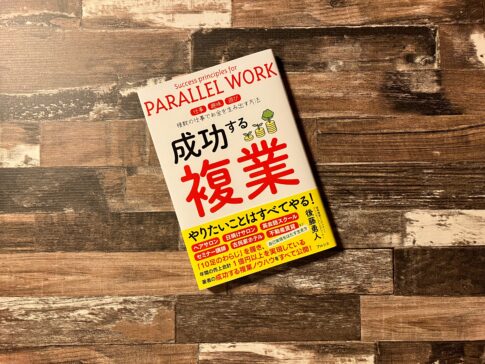




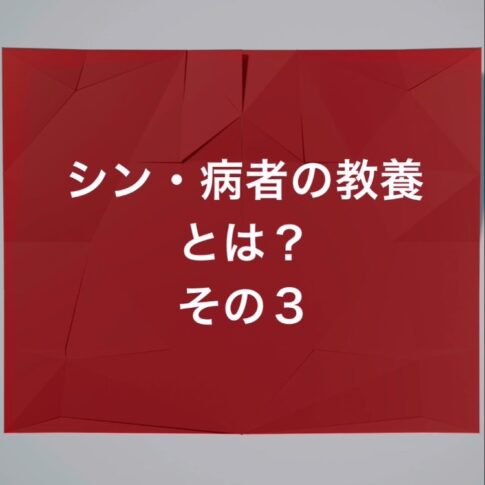
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。